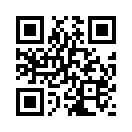2013年01月20日
知られざる大日堂舞楽
こんにちは!石けん小母さんです。
明けましておめでとうございます。新年初の投稿となります。ご高覧頂いている皆さま、本年もよろしくお願いいたします。
さて、タイトルにも挙げましたが、この度石けん小母さんが取材させて頂いたのは毎年1月2日に八幡平小豆沢にある「大日霊神社(おおひるめむちじんじゃ)」に奉納される「大日堂舞楽」が、神社に到着するまでの部分です。
4集落(大里、小豆沢、長嶺、谷内)のうち、小豆沢集落の能衆の皆さんの様子を取材させて頂き、「権現舞」を中心にお話を伺いました。
毎年12月15日より役目に応じて順に「行(ぎょう)」と言われる「禊(みそぎ)」に入ります。これは能衆が神様に近づくため、身を清めるのだそうで、食事や普段の生活を俗世から断つ風習です。それと同時に、それぞれ舞の稽古、内習(うちならい)に入ります。小豆沢集落では、12月26日から「大日霊神社」において合同練習に入ります。

年が明けて元旦の夕方に小豆沢の「平安神社」で「身固めの舞」を奉納し、本番に向けて志気を高めていきます。

そしていよいよ2日の午前1時半。「お宿」といわれるお宅に集合し、能衆の皆でお膳を頂きます(このとき女性はその座敷の敷居を跨ぐことが出来ません)。石けん小母さんは遠くから拝見しました。

午前3時を回った頃、能衆の皆さんはお宿の庭で「水垢離(みずごり)」を始めます。この日の気温は氷点下。。。
「1月、2月・・・12月」との掛け声とともに12回、凍て付く中で水を浴び、身を清め、装束に袖を通します。


新しい藁で編んだ藁靴を履き、お神酒を頂き、祈祷した後、お宿に感謝し繫栄を祝い舞を奉納します。


お宿を後に、集落の中を歩いて「平安神社」、「笛吹田」、「天王」さん、「白山」さんを順に廻り舞を奉納し、大里集落と合流し「西のカクチ」の斎場で霊山である「五宮嶽」に向い舞を奉納し、いよいよ「大日霊神社」へ。

ここから先は、皆さんご存じの通りの、大日堂舞楽となります。

今年は昨年に引き続き「道の駅かづのから」シャトルバスが運行され、早朝にもかかわらず多くの参拝者で賑わいました。
近年、様々なメディアで取り上げられるようになり、少しずつ知られるようになった鹿角市八幡平の「大日堂舞楽」。
今回の取材を通して感じたのは、今まで機会が無くまだご覧になっていない方、ご興味を持たれた方に、来年はぜひ足をお運び頂き、実際に目で、肌で、伝統行事を感じて頂きたいと思いました。
*石けん小母さん*
明けましておめでとうございます。新年初の投稿となります。ご高覧頂いている皆さま、本年もよろしくお願いいたします。
さて、タイトルにも挙げましたが、この度石けん小母さんが取材させて頂いたのは毎年1月2日に八幡平小豆沢にある「大日霊神社(おおひるめむちじんじゃ)」に奉納される「大日堂舞楽」が、神社に到着するまでの部分です。
4集落(大里、小豆沢、長嶺、谷内)のうち、小豆沢集落の能衆の皆さんの様子を取材させて頂き、「権現舞」を中心にお話を伺いました。
毎年12月15日より役目に応じて順に「行(ぎょう)」と言われる「禊(みそぎ)」に入ります。これは能衆が神様に近づくため、身を清めるのだそうで、食事や普段の生活を俗世から断つ風習です。それと同時に、それぞれ舞の稽古、内習(うちならい)に入ります。小豆沢集落では、12月26日から「大日霊神社」において合同練習に入ります。

年が明けて元旦の夕方に小豆沢の「平安神社」で「身固めの舞」を奉納し、本番に向けて志気を高めていきます。

そしていよいよ2日の午前1時半。「お宿」といわれるお宅に集合し、能衆の皆でお膳を頂きます(このとき女性はその座敷の敷居を跨ぐことが出来ません)。石けん小母さんは遠くから拝見しました。

午前3時を回った頃、能衆の皆さんはお宿の庭で「水垢離(みずごり)」を始めます。この日の気温は氷点下。。。
「1月、2月・・・12月」との掛け声とともに12回、凍て付く中で水を浴び、身を清め、装束に袖を通します。


新しい藁で編んだ藁靴を履き、お神酒を頂き、祈祷した後、お宿に感謝し繫栄を祝い舞を奉納します。


お宿を後に、集落の中を歩いて「平安神社」、「笛吹田」、「天王」さん、「白山」さんを順に廻り舞を奉納し、大里集落と合流し「西のカクチ」の斎場で霊山である「五宮嶽」に向い舞を奉納し、いよいよ「大日霊神社」へ。

ここから先は、皆さんご存じの通りの、大日堂舞楽となります。

今年は昨年に引き続き「道の駅かづのから」シャトルバスが運行され、早朝にもかかわらず多くの参拝者で賑わいました。
近年、様々なメディアで取り上げられるようになり、少しずつ知られるようになった鹿角市八幡平の「大日堂舞楽」。
今回の取材を通して感じたのは、今まで機会が無くまだご覧になっていない方、ご興味を持たれた方に、来年はぜひ足をお運び頂き、実際に目で、肌で、伝統行事を感じて頂きたいと思いました。
*石けん小母さん*
Posted by のんびり探検隊 at 08:30│Comments(6)
│イベント
この記事へのコメント
大日堂舞楽は神聖な行事であることの実態を初めて知りました。子供の頃の凧男は舞楽よりも大日堂周辺の出店で古本を買ったりおいしい菓子を食べたりしていました。「白山家」は凧男の総本家であります。
Posted by 凧男 at 2013年01月21日 20:18
凧男さま、コメントありがとうございます。
現在同じ地域に暮らしていても、「行」や大日堂での「奉納舞」の様子以外については、世襲制などもあり広く知られてはいません。
今回の取材がなければ、私も知ることはありませんでしたので、とても貴重な体験でした。
今年も境内では出店があり、本番中は賑やかでしたよ。
凧男さんは「白山家」系統の方なんですね。帰省の機会がありましたらぜひご覧頂きたいと思います。
現在同じ地域に暮らしていても、「行」や大日堂での「奉納舞」の様子以外については、世襲制などもあり広く知られてはいません。
今回の取材がなければ、私も知ることはありませんでしたので、とても貴重な体験でした。
今年も境内では出店があり、本番中は賑やかでしたよ。
凧男さんは「白山家」系統の方なんですね。帰省の機会がありましたらぜひご覧頂きたいと思います。
Posted by のんびり探検隊 at 2013年01月23日 09:25
at 2013年01月23日 09:25
 at 2013年01月23日 09:25
at 2013年01月23日 09:25“大日堂舞楽”以前から知っていますよ。
こちらでも報道されていました。
1月2日に行われる鹿角の伝統的な正月行事ですよね。
こういう古き良き郷土芸能を末永く守って欲しいものです。
鹿角の方達にとってこれは、お正月の拠り所となる
伝統行事ですよね。
こちらでも報道されていました。
1月2日に行われる鹿角の伝統的な正月行事ですよね。
こういう古き良き郷土芸能を末永く守って欲しいものです。
鹿角の方達にとってこれは、お正月の拠り所となる
伝統行事ですよね。
Posted by JG7MER / Ackee at 2013年01月27日 12:15
JG7MER / Ackeeさま
コメントありがとうございます。
大日堂舞楽について、お詳しい方のようで嬉しいです!
今回は、テレビや新聞にはなかなか取り上げられない部分を皆さんにも知って頂きたく、密着取材させて頂きました。
1300年続く伝統行事ですが、1月2日早朝の、しかも八幡平地域の行事なので、鹿角市内でも、まだまだ本番を見たことのない市民もいるんですよ~。
機会がありましたらぜひ見にいらしてください!!
コメントありがとうございます。
大日堂舞楽について、お詳しい方のようで嬉しいです!
今回は、テレビや新聞にはなかなか取り上げられない部分を皆さんにも知って頂きたく、密着取材させて頂きました。
1300年続く伝統行事ですが、1月2日早朝の、しかも八幡平地域の行事なので、鹿角市内でも、まだまだ本番を見たことのない市民もいるんですよ~。
機会がありましたらぜひ見にいらしてください!!
Posted by のんびり探検隊 at 2013年01月29日 17:17
at 2013年01月29日 17:17
 at 2013年01月29日 17:17
at 2013年01月29日 17:17コメントありがとうございます。
旧八幡平村管轄の伝統行事ですよね。
小豆沢の方が分り易いです。
詳細については今回、初めて分りました。
これとちょっと似た行事が宮城にもあります。
1月14日はお正月のしめ飾りを焼く小正月行事、
“どんと祭”と云うのが仙台を中心に宮城県内各地の
神社で行われます。
確か石巻地域のとある集落で子供達がお宮の中に泊まり、14日に集落地域を一軒一軒回る小正月行事があります。確か『えんずの割』と云う伝統芸能です。
木の棒を地面に打ち付けて「えんずのわ~り!!えんずのわ~り!!」と言いながら、子供達が装束を身に纏い民家を一軒一軒廻る様です。これは何でも農作物を食い荒らす鳥を追い払う事から始まった様で、一年の農作物の五穀豊穣を願っての伝統行事だそうです。只、東日本大震災の影響で今年はやったのか?
ローカルニュースでは聞いていませんが…。
旧八幡平村管轄の伝統行事ですよね。
小豆沢の方が分り易いです。
詳細については今回、初めて分りました。
これとちょっと似た行事が宮城にもあります。
1月14日はお正月のしめ飾りを焼く小正月行事、
“どんと祭”と云うのが仙台を中心に宮城県内各地の
神社で行われます。
確か石巻地域のとある集落で子供達がお宮の中に泊まり、14日に集落地域を一軒一軒回る小正月行事があります。確か『えんずの割』と云う伝統芸能です。
木の棒を地面に打ち付けて「えんずのわ~り!!えんずのわ~り!!」と言いながら、子供達が装束を身に纏い民家を一軒一軒廻る様です。これは何でも農作物を食い荒らす鳥を追い払う事から始まった様で、一年の農作物の五穀豊穣を願っての伝統行事だそうです。只、東日本大震災の影響で今年はやったのか?
ローカルニュースでは聞いていませんが…。
Posted by JG7MER / Ackee at 2013年01月29日 22:54
JG7MER / Ackeeさま
各地には、無病息災、五穀豊穣などを祈願する伝統行事がたくさん残っているんですね。
震災後、様々な理由で継続が難しい中、こうして例年同様開催できる環境に感謝したいと思います。
各地には、無病息災、五穀豊穣などを祈願する伝統行事がたくさん残っているんですね。
震災後、様々な理由で継続が難しい中、こうして例年同様開催できる環境に感謝したいと思います。
Posted by のんびり探検隊 at 2013年01月30日 09:14
at 2013年01月30日 09:14
 at 2013年01月30日 09:14
at 2013年01月30日 09:14※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。