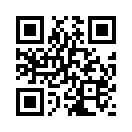2012年11月21日
鹿角の庚申さんめぐり
道ばたや集落のはずれにあって、昔から気になっていたコーシンさん。
調べてみると、江戸時代の風習で、庚申(かのえさる)の日というのが60日に1度まわってきて、人々がその日に集まり夜を徹して悪い虫が天に昇るのを防いだといいます。これを庚申講といい、3年間18回行うと石碑を建てたのだそうです。

※ 集落のはずれ 分かれ道にぽつんと。 (十和田大湯)

※ 下の方は埋もれてしまいました。 (八幡平松館)

※ 後ろに神社が建てられているものも多い。 (尾去沢西道口)

※ 庚申さんそのものが祭られている所もある。 (花輪小平)
基本アイテムは「庚申」の字が彫られた石碑に柳の大木。しかし、江戸時代からの柳は朽ちてしまって伐採された所がほとんどで、後の人々が杉や桜などを植えている所が多いようです。私の知っている所では、花輪鶴田、十和田末広に昔からの柳が残っています。3年ほど前まで十和田草木にもありましたが「倒木注意」で切られてしまいました。

※ かなり早い時期に新道ができたので、良い保存状態で残ったのでしょう。 (十和田末広)

※ だいぶ朽ちてきて、近所の人がつっかえ棒をしてくれています。 (花輪鶴田)


※ 上下は同じ場所ですが(上は電柱の陰が庚申さん)、なるほど昭和30年代の写真を見ると柳の大木が立っていますね。オート三輪が時代を感じさせます。 (十和田毛馬内)

※ 柳の木にはクワガタムシがいるので、小学生の頃には根元を掘り返し、ここの庚申さんを倒して叱られたものです。今ではコンクリートで固定されています。 (十和田毛馬内)

※ わが集落の庚申さんです。なかなか立派なものです。数年前に桜の木が切られてしまいました。 (十和田毛馬内)
皆さんもお暇なときにのんびり探してみてください。旧道沿いならどこにでもあります。庚申さんは時を超えて私たちに無病息災を願う人々の心を伝えてくれます。
浦島次郎でした。
調べてみると、江戸時代の風習で、庚申(かのえさる)の日というのが60日に1度まわってきて、人々がその日に集まり夜を徹して悪い虫が天に昇るのを防いだといいます。これを庚申講といい、3年間18回行うと石碑を建てたのだそうです。

※ 集落のはずれ 分かれ道にぽつんと。 (十和田大湯)

※ 下の方は埋もれてしまいました。 (八幡平松館)

※ 後ろに神社が建てられているものも多い。 (尾去沢西道口)

※ 庚申さんそのものが祭られている所もある。 (花輪小平)
基本アイテムは「庚申」の字が彫られた石碑に柳の大木。しかし、江戸時代からの柳は朽ちてしまって伐採された所がほとんどで、後の人々が杉や桜などを植えている所が多いようです。私の知っている所では、花輪鶴田、十和田末広に昔からの柳が残っています。3年ほど前まで十和田草木にもありましたが「倒木注意」で切られてしまいました。

※ かなり早い時期に新道ができたので、良い保存状態で残ったのでしょう。 (十和田末広)

※ だいぶ朽ちてきて、近所の人がつっかえ棒をしてくれています。 (花輪鶴田)


※ 上下は同じ場所ですが(上は電柱の陰が庚申さん)、なるほど昭和30年代の写真を見ると柳の大木が立っていますね。オート三輪が時代を感じさせます。 (十和田毛馬内)

※ 柳の木にはクワガタムシがいるので、小学生の頃には根元を掘り返し、ここの庚申さんを倒して叱られたものです。今ではコンクリートで固定されています。 (十和田毛馬内)

※ わが集落の庚申さんです。なかなか立派なものです。数年前に桜の木が切られてしまいました。 (十和田毛馬内)
皆さんもお暇なときにのんびり探してみてください。旧道沿いならどこにでもあります。庚申さんは時を超えて私たちに無病息災を願う人々の心を伝えてくれます。
浦島次郎でした。