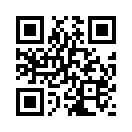2013年01月20日
知られざる大日堂舞楽
こんにちは!石けん小母さんです。
明けましておめでとうございます。新年初の投稿となります。ご高覧頂いている皆さま、本年もよろしくお願いいたします。
さて、タイトルにも挙げましたが、この度石けん小母さんが取材させて頂いたのは毎年1月2日に八幡平小豆沢にある「大日霊神社(おおひるめむちじんじゃ)」に奉納される「大日堂舞楽」が、神社に到着するまでの部分です。
4集落(大里、小豆沢、長嶺、谷内)のうち、小豆沢集落の能衆の皆さんの様子を取材させて頂き、「権現舞」を中心にお話を伺いました。
毎年12月15日より役目に応じて順に「行(ぎょう)」と言われる「禊(みそぎ)」に入ります。これは能衆が神様に近づくため、身を清めるのだそうで、食事や普段の生活を俗世から断つ風習です。それと同時に、それぞれ舞の稽古、内習(うちならい)に入ります。小豆沢集落では、12月26日から「大日霊神社」において合同練習に入ります。

年が明けて元旦の夕方に小豆沢の「平安神社」で「身固めの舞」を奉納し、本番に向けて志気を高めていきます。

そしていよいよ2日の午前1時半。「お宿」といわれるお宅に集合し、能衆の皆でお膳を頂きます(このとき女性はその座敷の敷居を跨ぐことが出来ません)。石けん小母さんは遠くから拝見しました。

午前3時を回った頃、能衆の皆さんはお宿の庭で「水垢離(みずごり)」を始めます。この日の気温は氷点下。。。
「1月、2月・・・12月」との掛け声とともに12回、凍て付く中で水を浴び、身を清め、装束に袖を通します。


新しい藁で編んだ藁靴を履き、お神酒を頂き、祈祷した後、お宿に感謝し繫栄を祝い舞を奉納します。


お宿を後に、集落の中を歩いて「平安神社」、「笛吹田」、「天王」さん、「白山」さんを順に廻り舞を奉納し、大里集落と合流し「西のカクチ」の斎場で霊山である「五宮嶽」に向い舞を奉納し、いよいよ「大日霊神社」へ。

ここから先は、皆さんご存じの通りの、大日堂舞楽となります。

今年は昨年に引き続き「道の駅かづのから」シャトルバスが運行され、早朝にもかかわらず多くの参拝者で賑わいました。
近年、様々なメディアで取り上げられるようになり、少しずつ知られるようになった鹿角市八幡平の「大日堂舞楽」。
今回の取材を通して感じたのは、今まで機会が無くまだご覧になっていない方、ご興味を持たれた方に、来年はぜひ足をお運び頂き、実際に目で、肌で、伝統行事を感じて頂きたいと思いました。
*石けん小母さん*
明けましておめでとうございます。新年初の投稿となります。ご高覧頂いている皆さま、本年もよろしくお願いいたします。
さて、タイトルにも挙げましたが、この度石けん小母さんが取材させて頂いたのは毎年1月2日に八幡平小豆沢にある「大日霊神社(おおひるめむちじんじゃ)」に奉納される「大日堂舞楽」が、神社に到着するまでの部分です。
4集落(大里、小豆沢、長嶺、谷内)のうち、小豆沢集落の能衆の皆さんの様子を取材させて頂き、「権現舞」を中心にお話を伺いました。
毎年12月15日より役目に応じて順に「行(ぎょう)」と言われる「禊(みそぎ)」に入ります。これは能衆が神様に近づくため、身を清めるのだそうで、食事や普段の生活を俗世から断つ風習です。それと同時に、それぞれ舞の稽古、内習(うちならい)に入ります。小豆沢集落では、12月26日から「大日霊神社」において合同練習に入ります。

年が明けて元旦の夕方に小豆沢の「平安神社」で「身固めの舞」を奉納し、本番に向けて志気を高めていきます。

そしていよいよ2日の午前1時半。「お宿」といわれるお宅に集合し、能衆の皆でお膳を頂きます(このとき女性はその座敷の敷居を跨ぐことが出来ません)。石けん小母さんは遠くから拝見しました。

午前3時を回った頃、能衆の皆さんはお宿の庭で「水垢離(みずごり)」を始めます。この日の気温は氷点下。。。
「1月、2月・・・12月」との掛け声とともに12回、凍て付く中で水を浴び、身を清め、装束に袖を通します。


新しい藁で編んだ藁靴を履き、お神酒を頂き、祈祷した後、お宿に感謝し繫栄を祝い舞を奉納します。


お宿を後に、集落の中を歩いて「平安神社」、「笛吹田」、「天王」さん、「白山」さんを順に廻り舞を奉納し、大里集落と合流し「西のカクチ」の斎場で霊山である「五宮嶽」に向い舞を奉納し、いよいよ「大日霊神社」へ。

ここから先は、皆さんご存じの通りの、大日堂舞楽となります。

今年は昨年に引き続き「道の駅かづのから」シャトルバスが運行され、早朝にもかかわらず多くの参拝者で賑わいました。
近年、様々なメディアで取り上げられるようになり、少しずつ知られるようになった鹿角市八幡平の「大日堂舞楽」。
今回の取材を通して感じたのは、今まで機会が無くまだご覧になっていない方、ご興味を持たれた方に、来年はぜひ足をお運び頂き、実際に目で、肌で、伝統行事を感じて頂きたいと思いました。
*石けん小母さん*