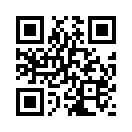2011年01月02日
大日堂舞楽(だいにちどうぶがく)
新年になりました
本年も 十和田八幡平『のんびり探検隊』
のブログを宜しくお願いいたします。
さすらいのライダーです

新年2日に行われた、ユネスコ無形文化遺産に登録されている(2009年)
「国指定重要無形民族文化財 大日堂舞楽」に行ってきました
場所は秋田県鹿角市八幡平 大日堂(JR花輪線 八幡平駅から徒歩1分)
八幡平の大日堂で正月の2日に演じられる芸能です。都から下向した楽人
によって伝えられた舞楽がその起源とされている。はるか奈良時代まで
さかのぼる
4集落の能集による「神子舞」「神名手舞」
小豆沢(あずきさわ) の「権現舞」と「田楽舞」
大里(おおさと) の「駒舞」「鳥舞」「工匠舞」
長峰(ながみね) の「鳥遍舞」
谷内(たにない) の「五大尊舞」
の9演目が伝承されており、仮面をつけたり採物を持つなどして
笛や太鼓の囃子で舞われている
詳しくは http://www.ink.or.jp/~hatakei/ でも見ることが
出来ます
大日堂(だいにちどう)の外部

大日堂の内部

平安神社での奉納 マイナス7℃でした 7:39分

平安神社から大日堂「大日霊貴神社(おおひるめむちじんじゃ)」に向けて隊列
路面は凍結 アイスバーン状態です 7:47分

4つの集落が大日堂姥杉前に集合 修祓の儀(しゅばつのぎ) 8:00分
地蔵舞(権現舞)を奉納

幡綜(はたへい) 4集落の能衆勢ぞろい 8:10分
花舞(神子舞・みこまい、神名手舞・かなてまい、権現舞・ごんげんまい)
籾押し(もみおし) 若者10数人の威勢のよい掛け声でした 8:39分
御上楽(ごじょうらく)

幡上げ(はたあげ) 幡持ちが堂内に走り込み、幡をひらめかせて下からさし
上げると、二階のものが受け取り、さらに梁に投げ上げ、梁のものは
直ちにこれを欄干から下げます
(籾押しの若者が堂内(二手に別れ、一方は東方殿上に、もう一方は
西方殿上にのぼり、旗上げに備えています) 8:48分

本舞の前に行われる 籾押し・御上楽と幡上げ
そして、神子舞(みこまい)、神名手舞(かなてまい)、大小行事、修法(祭式)が
行われて、本舞へと
本舞
権現舞(ごんげんまい) 小豆沢能衆 9:40分
継体天皇と吉祥姫との間に出来た五ノ宮皇子(ごのみやおうじ)が五ノ宮嶽
に登り、そのまま姿を消したという伝説によるもので、五ノ宮嶽の隣に
そびえる八森岳に龍が出て、それを鎮めるために獅子頭を奉納したのが
舞の起源といわれています

駒舞(こままい) 大里能衆二人 10:04分
大日堂再建の時に天皇から下された駿馬二頭をあらわすとも、五ノ宮皇子の
乗馬である月毛の馬をあらわす舞ともいわれています

烏遍舞(うへんまい) 長嶺の能衆6名 10:29分
継体天皇の後宮であった吉祥姫の遺体を葬る様を舞にしたものといわれ、
「墓固めの舞」とも呼ばれています
最後に大博士、小博士は、持っていたお守りを参拝者に撒きます
このお守りを拾ったものは山仕事によいことがあり、その年の
大運を拾うといわれています

鳥舞(とりまい) 大里の3人の子供 10:47分
だんぶり長者が飼っていた鳥の舞といわれています

五大尊舞(ごだいそんまい) 谷内能衆6人 11:02分
金剛界大日如来(こんごうかいだいにちにょらい)、胎蔵界大日如来
(たいぞうかいだいにちにょらい)がだんぶり長者に化身し、それに
普賢(ふげん)、八幡(はちまん)、文殊(もんじゅ)、不動(ふどう)、
の四大明王が仕えた様をあらわしているといわれています
黄金の仮面の能衆が2人で・・・。 凄かった!

工匠舞(こうしょうまい) 大里能衆4人 11:34分
大日堂霊貴神の御神体を彫刻する姿を舞い表わした匠の舞といわれています

田楽舞(でんがくまい) 小豆沢能衆6名 11:46分
だんぶり長者夫婦が農夫の耕作の労を慰めるために舞われたとも、
農耕の様子を表現した舞であるともいわれています
この田楽舞は、日本各地の田楽舞のなかでも最古のものといわれています

厳寒の凍てつく寒さのなか(-7℃)本当にお疲れ様でした
とても素晴らしい舞楽でした。画像をもっと大きく沢山載せたかった
実際は昨年12月半ばから舞楽は始まっていました。とても全部を伝えること
が出来ないのが残念です。朝方6:00から見ていましたが、2日は0:30から
舞楽が始まっていると聞きました。
寒さ対策をして、来年の正月2日に見に来てください

本年も 十和田八幡平『のんびり探検隊』
のブログを宜しくお願いいたします。
さすらいのライダーです


新年2日に行われた、ユネスコ無形文化遺産に登録されている(2009年)
「国指定重要無形民族文化財 大日堂舞楽」に行ってきました

場所は秋田県鹿角市八幡平 大日堂(JR花輪線 八幡平駅から徒歩1分)
八幡平の大日堂で正月の2日に演じられる芸能です。都から下向した楽人
によって伝えられた舞楽がその起源とされている。はるか奈良時代まで
さかのぼる
4集落の能集による「神子舞」「神名手舞」
小豆沢(あずきさわ) の「権現舞」と「田楽舞」
大里(おおさと) の「駒舞」「鳥舞」「工匠舞」
長峰(ながみね) の「鳥遍舞」
谷内(たにない) の「五大尊舞」
の9演目が伝承されており、仮面をつけたり採物を持つなどして
笛や太鼓の囃子で舞われている
詳しくは http://www.ink.or.jp/~hatakei/ でも見ることが
出来ます
大日堂(だいにちどう)の外部

大日堂の内部

平安神社での奉納 マイナス7℃でした 7:39分

平安神社から大日堂「大日霊貴神社(おおひるめむちじんじゃ)」に向けて隊列
路面は凍結 アイスバーン状態です 7:47分

4つの集落が大日堂姥杉前に集合 修祓の儀(しゅばつのぎ) 8:00分
地蔵舞(権現舞)を奉納

幡綜(はたへい) 4集落の能衆勢ぞろい 8:10分
花舞(神子舞・みこまい、神名手舞・かなてまい、権現舞・ごんげんまい)
籾押し(もみおし) 若者10数人の威勢のよい掛け声でした 8:39分
御上楽(ごじょうらく)

幡上げ(はたあげ) 幡持ちが堂内に走り込み、幡をひらめかせて下からさし
上げると、二階のものが受け取り、さらに梁に投げ上げ、梁のものは
直ちにこれを欄干から下げます
(籾押しの若者が堂内(二手に別れ、一方は東方殿上に、もう一方は
西方殿上にのぼり、旗上げに備えています) 8:48分

本舞の前に行われる 籾押し・御上楽と幡上げ
そして、神子舞(みこまい)、神名手舞(かなてまい)、大小行事、修法(祭式)が
行われて、本舞へと
本舞
権現舞(ごんげんまい) 小豆沢能衆 9:40分
継体天皇と吉祥姫との間に出来た五ノ宮皇子(ごのみやおうじ)が五ノ宮嶽
に登り、そのまま姿を消したという伝説によるもので、五ノ宮嶽の隣に
そびえる八森岳に龍が出て、それを鎮めるために獅子頭を奉納したのが
舞の起源といわれています

駒舞(こままい) 大里能衆二人 10:04分
大日堂再建の時に天皇から下された駿馬二頭をあらわすとも、五ノ宮皇子の
乗馬である月毛の馬をあらわす舞ともいわれています

烏遍舞(うへんまい) 長嶺の能衆6名 10:29分
継体天皇の後宮であった吉祥姫の遺体を葬る様を舞にしたものといわれ、
「墓固めの舞」とも呼ばれています
最後に大博士、小博士は、持っていたお守りを参拝者に撒きます
このお守りを拾ったものは山仕事によいことがあり、その年の
大運を拾うといわれています

鳥舞(とりまい) 大里の3人の子供 10:47分
だんぶり長者が飼っていた鳥の舞といわれています

五大尊舞(ごだいそんまい) 谷内能衆6人 11:02分
金剛界大日如来(こんごうかいだいにちにょらい)、胎蔵界大日如来
(たいぞうかいだいにちにょらい)がだんぶり長者に化身し、それに
普賢(ふげん)、八幡(はちまん)、文殊(もんじゅ)、不動(ふどう)、
の四大明王が仕えた様をあらわしているといわれています
黄金の仮面の能衆が2人で・・・。 凄かった!

工匠舞(こうしょうまい) 大里能衆4人 11:34分
大日堂霊貴神の御神体を彫刻する姿を舞い表わした匠の舞といわれています

田楽舞(でんがくまい) 小豆沢能衆6名 11:46分
だんぶり長者夫婦が農夫の耕作の労を慰めるために舞われたとも、
農耕の様子を表現した舞であるともいわれています
この田楽舞は、日本各地の田楽舞のなかでも最古のものといわれています

厳寒の凍てつく寒さのなか(-7℃)本当にお疲れ様でした

とても素晴らしい舞楽でした。画像をもっと大きく沢山載せたかった

実際は昨年12月半ばから舞楽は始まっていました。とても全部を伝えること
が出来ないのが残念です。朝方6:00から見ていましたが、2日は0:30から
舞楽が始まっていると聞きました。
寒さ対策をして、来年の正月2日に見に来てください

Posted by のんびり探検隊 at 17:40│Comments(6)
│祭
この記事へのコメント
大日堂の傍で幼少期を過ごした凧男には涙が出るほどなつかしい映像でした。「よんやら、やあい、そりゃん、さーい」という「籾押し」の掛け声が脳裏に浮かびます。大日堂のことは「おど」舞楽のことは「じぇえど」と呼んでいました。また当日は大日堂の周囲には多くの露店が並んでいました。お年玉を握りしめてお菓子や古本を買った記憶があります。懐かしくて懐かしくて涙が出ました。「故郷は遠くにありて想うもの…」です。また、涙です。
Posted by 凧男 at 2011年01月03日 05:53
明けましておめでとうございます☆
私は秋田の温泉が大好きで、秋田にとても興味があり、去年よりこちらのブログをロムさせてもらってます(*^_^*)
温泉以外にも、秋田県は沢山興味深いものがあることを、こちらで知る事ができました。
先日の新聞に、男鹿半島のなまはげの記事は出ていましたが、この大日堂舞樂の事は何も情報はなく、こちらで初めて知りました。秋田にはとても素敵な伝統舞楽があるものなんですね。
今年も隊員方の面白い情報や、ためになる情報を楽しみに毎日ロムさせてもらいますね♪
私は秋田の温泉が大好きで、秋田にとても興味があり、去年よりこちらのブログをロムさせてもらってます(*^_^*)
温泉以外にも、秋田県は沢山興味深いものがあることを、こちらで知る事ができました。
先日の新聞に、男鹿半島のなまはげの記事は出ていましたが、この大日堂舞樂の事は何も情報はなく、こちらで初めて知りました。秋田にはとても素敵な伝統舞楽があるものなんですね。
今年も隊員方の面白い情報や、ためになる情報を楽しみに毎日ロムさせてもらいますね♪
Posted by ごえもん at 2011年01月03日 23:48
凧男さんへ
「よんやら、やあい、そりゃん、さーい」という「籾押し」の掛け声が脳裏に浮かびます。大日堂のことは「おど」舞楽のことは「じぇえど」
こんなかけ声が迫力がありました。ちょっとびっくりでした。
また旗揚げも素晴らしいかけ声とともに! 観光PR誌などでは感じ取れないことを沢山見ることができました。
凧男さんは分かると思いますが、12月28日の夜7:00に奉納された大権現様と姥権現様の舞に子供達が来てて、おさいせんを拾ったり、御菓子を食べたり、飲み物を飲んだりそんな光景が私は印象的でした。そんな光景も公開したかったんですけど、1部分だけの公開となりました。 懐かしんでいただいて有難うございました。
「よんやら、やあい、そりゃん、さーい」という「籾押し」の掛け声が脳裏に浮かびます。大日堂のことは「おど」舞楽のことは「じぇえど」
こんなかけ声が迫力がありました。ちょっとびっくりでした。
また旗揚げも素晴らしいかけ声とともに! 観光PR誌などでは感じ取れないことを沢山見ることができました。
凧男さんは分かると思いますが、12月28日の夜7:00に奉納された大権現様と姥権現様の舞に子供達が来てて、おさいせんを拾ったり、御菓子を食べたり、飲み物を飲んだりそんな光景が私は印象的でした。そんな光景も公開したかったんですけど、1部分だけの公開となりました。 懐かしんでいただいて有難うございました。
Posted by さすらいのライダーより at 2011年01月04日 09:08
ごえもんさんへ
私も初めて見ました。沢山のことを見ましたが全部を伝えることが出来ませんでした。祭は前年から始まっていました。1月2日は総集編みたいでした。厳寒の朝方から舞を奉納する能衆(ざいどうとも呼ばれている)の心意気を感じました。また機会があれば裏の(もう一つの大日堂舞楽)風景も取材したいと思っています。コメント有難うございました。
私も初めて見ました。沢山のことを見ましたが全部を伝えることが出来ませんでした。祭は前年から始まっていました。1月2日は総集編みたいでした。厳寒の朝方から舞を奉納する能衆(ざいどうとも呼ばれている)の心意気を感じました。また機会があれば裏の(もう一つの大日堂舞楽)風景も取材したいと思っています。コメント有難うございました。
Posted by さすらいのライダーより at 2011年01月04日 09:17
〝お祭り大国〟(神社本庁が以前行った「全国祭祀祭礼総合調査」によると、その数は全国で三十万件)のなかでユネスコ無形文化遺産に登録されているとは凄いのだろうと思うだけで想像もつきませんでした。この記事を見て内容を知ることができました。長い歴史をもつ伝統行事の能衆は当日に備えて大変な努力をされるのでしょうね。画像から厳寒のなかでの迫力が伝わりますが、実際に見ていたらもっといろんなものが伝わるのでしょうね。
Posted by ドリ at 2011年01月04日 16:06
ドリさんへ
いつもコメントありがとうございます。この舞楽はだんぶり長者伝説から始まっています。奈良時代からなので1000数百年以上前から伝わっていて、いまなお継承しているざいどう能衆に感動しました。夫婦、親子、集落、みんなで支えて来た舞楽というのが良くわかりました。見せるための舞楽は正月一月二日ですが、前後の種々な行事は集落のお祭りであり、素朴なものでした。きらびやかな見せる場面も多くありますが、素朴なところもたくさんありました。
厳寒のなか、見ているだけでも寒かったんですが、ざいどう能衆のかただたには敬意を表したい気持ちでいっぱいでした。
ドリさんもいつか時間がありましたらお越しくださいませ。
いつもコメントありがとうございます。この舞楽はだんぶり長者伝説から始まっています。奈良時代からなので1000数百年以上前から伝わっていて、いまなお継承しているざいどう能衆に感動しました。夫婦、親子、集落、みんなで支えて来た舞楽というのが良くわかりました。見せるための舞楽は正月一月二日ですが、前後の種々な行事は集落のお祭りであり、素朴なものでした。きらびやかな見せる場面も多くありますが、素朴なところもたくさんありました。
厳寒のなか、見ているだけでも寒かったんですが、ざいどう能衆のかただたには敬意を表したい気持ちでいっぱいでした。
ドリさんもいつか時間がありましたらお越しくださいませ。
Posted by さすらいのライダーより at 2011年01月04日 17:16
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。