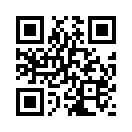2010年11月21日
菅江真澄の道~毛馬内から小坂周辺~
前に真澄の跡を追って、錦木から柴平周辺を訪れました。今回は毛馬内から十和田湖へ向かった真澄の跡を訪ねます。
文化4年(1807)8月19日、真澄は毛馬内を発ちます。
「しるけ川を渡った。この川上は瀬が二つになった流れで、川の屈曲したところに、むかし長者の館があって、朝飯夕飯の鍋を数多く洗うために、いつも水がすこし濁って汁気があるところからいいはじめた名である。」


「万谷、荒川の部落を左手にみて、牛馬長根の尾根をひとつ越えると、弥五兵衛初立という村がある。武田の館があったころ、西町の検断(罪人をとりしまる役)であったその名の人がここにきて、田畠をつくり、一族もひろく栄え、このような村になって、山の名をいまはもっぱら「うしまながね」とよんでいる。」

「子坂村を過ぎると、鳥越という部落がある。どの家の門口にも、しめなわをはったり、あるいは地獄茨(サルトリイバラ)というものをひきまわし、また葦の長い根もひき渡して、それに皀角子(サイカチ)・くれのをも(ウイキョウ)もさしそえてある。また、くさ人形のささやかなものを二つ作って、剣をもたせ、蕃椒(トウガラシ)を角にして、これを男女の鬼になぞらえて疫病よけのおまじないものとしていた。」


「朱鷺(ときとお 鴇)という村が右方に見えた。左手に杜があり、馬櫪神を祀っている。」

鴇を発った真澄は、その後藤原(七滝)、砂子沢を経由して十曲湖(十和田湖)に向かい、8月29日に休屋附近に到着するのです。
真澄がこのように事細かに記録を残してくれたおかげで、今でも当時の様子などを想像しながら、足跡を訪ねることができるのですね。
よっしーでした。
文化4年(1807)8月19日、真澄は毛馬内を発ちます。
「しるけ川を渡った。この川上は瀬が二つになった流れで、川の屈曲したところに、むかし長者の館があって、朝飯夕飯の鍋を数多く洗うために、いつも水がすこし濁って汁気があるところからいいはじめた名である。」


「万谷、荒川の部落を左手にみて、牛馬長根の尾根をひとつ越えると、弥五兵衛初立という村がある。武田の館があったころ、西町の検断(罪人をとりしまる役)であったその名の人がここにきて、田畠をつくり、一族もひろく栄え、このような村になって、山の名をいまはもっぱら「うしまながね」とよんでいる。」

「子坂村を過ぎると、鳥越という部落がある。どの家の門口にも、しめなわをはったり、あるいは地獄茨(サルトリイバラ)というものをひきまわし、また葦の長い根もひき渡して、それに皀角子(サイカチ)・くれのをも(ウイキョウ)もさしそえてある。また、くさ人形のささやかなものを二つ作って、剣をもたせ、蕃椒(トウガラシ)を角にして、これを男女の鬼になぞらえて疫病よけのおまじないものとしていた。」


「朱鷺(ときとお 鴇)という村が右方に見えた。左手に杜があり、馬櫪神を祀っている。」

鴇を発った真澄は、その後藤原(七滝)、砂子沢を経由して十曲湖(十和田湖)に向かい、8月29日に休屋附近に到着するのです。
真澄がこのように事細かに記録を残してくれたおかげで、今でも当時の様子などを想像しながら、足跡を訪ねることができるのですね。
よっしーでした。
Posted by のんびり探検隊 at 18:56│Comments(0)
│観光施設
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。