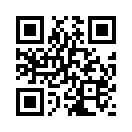2010年09月29日
菅江真澄の道~錦木から柴平周辺~
江戸期の紀行家、菅江真澄が鹿角を訪れた際の記録「けふのせば布」(天明5年=1785)から、その足跡の一部をたどってみました。
大館から鹿角を目指した真澄は、神田村(現在の鹿角市十和田末広字神田)に泊まり、翌八月二十七日に錦木塚を訪れます。
以下引用します。
「やがてここ(注:原文では古川を指し、現在の十和田錦木字古川)をでて、松の木村というところをくると、石の男根をならべた祠があった。これは、信濃、越後、出羽、とくに陸奥にたいへん多い。冠田村を経て涙川を渡る。鶴田を過ぎて、村の名を尋ねると、鉄砲とものものしく答えたので、戯れ歌をつくった。」
「石の男根を並べた祠」というのが面白そうですね。上の「松の木村」をクリックすると、地図に「金精神社」と見えますが、この神社のことです。

男根は社殿前に一基だけそそり立っています。真澄の時代にはもっとあったんでしょう。ただし、現在のものは木製ですので、本物は社殿内部にチン座しているのかもしれませんが、そとからは伺い知ることが出来ません。興味のある方は是非訪れてみてください。写真は撮ったのですが、わりとリアルなので、ここには載せないことにします。
面白いのはこの「金精神話訓」です。

うーむ、あやかりたいものですね・・・。もちろん拝みましたよ。
ところで、ここはかつての津軽(鹿角)街道(盛岡~花輪~大館~弘前)から来満街道(松の木~毛馬内~大湯~三戸)が分岐する地点になっていて、来満街道はこの金精神社の左脇から北進して毛馬内に入って東進し、三戸に通っていました。
金精神社内の標柱

来満街道入り口。たしかに古い街道らしき雰囲気が漂います。

冠田と鶴田の間にあった「涙川」というのはどこでしょう。現在この間には根市川と間瀬川の二つの川があるので、このいずれかでしょう。実際に見た感覚では、どうも根市川ではないかと思えます。なぜなら、間瀬川はいかにも人工的に作られたように見えるのに対し、根市川は自然の川のような気がするのです。間瀬川上流には導水路によって発電している柴平発電所もあり、真澄の時代には無かったのではないかと思えるのです。素人考えですが。
これが根市川です。私はこれが涙川だと思います。

こちらが間瀬川。人工的な感じがしませんか。

昔のことを知ると、普段気に留めなかった景色なども、違う見方が出来て面白いものですね。
よっしーでした。
大館から鹿角を目指した真澄は、神田村(現在の鹿角市十和田末広字神田)に泊まり、翌八月二十七日に錦木塚を訪れます。
以下引用します。
「やがてここ(注:原文では古川を指し、現在の十和田錦木字古川)をでて、松の木村というところをくると、石の男根をならべた祠があった。これは、信濃、越後、出羽、とくに陸奥にたいへん多い。冠田村を経て涙川を渡る。鶴田を過ぎて、村の名を尋ねると、鉄砲とものものしく答えたので、戯れ歌をつくった。」
「石の男根を並べた祠」というのが面白そうですね。上の「松の木村」をクリックすると、地図に「金精神社」と見えますが、この神社のことです。

男根は社殿前に一基だけそそり立っています。真澄の時代にはもっとあったんでしょう。ただし、現在のものは木製ですので、本物は社殿内部にチン座しているのかもしれませんが、そとからは伺い知ることが出来ません。興味のある方は是非訪れてみてください。写真は撮ったのですが、わりとリアルなので、ここには載せないことにします。
面白いのはこの「金精神話訓」です。

うーむ、あやかりたいものですね・・・。もちろん拝みましたよ。
ところで、ここはかつての津軽(鹿角)街道(盛岡~花輪~大館~弘前)から来満街道(松の木~毛馬内~大湯~三戸)が分岐する地点になっていて、来満街道はこの金精神社の左脇から北進して毛馬内に入って東進し、三戸に通っていました。
金精神社内の標柱

来満街道入り口。たしかに古い街道らしき雰囲気が漂います。

冠田と鶴田の間にあった「涙川」というのはどこでしょう。現在この間には根市川と間瀬川の二つの川があるので、このいずれかでしょう。実際に見た感覚では、どうも根市川ではないかと思えます。なぜなら、間瀬川はいかにも人工的に作られたように見えるのに対し、根市川は自然の川のような気がするのです。間瀬川上流には導水路によって発電している柴平発電所もあり、真澄の時代には無かったのではないかと思えるのです。素人考えですが。
これが根市川です。私はこれが涙川だと思います。

こちらが間瀬川。人工的な感じがしませんか。

昔のことを知ると、普段気に留めなかった景色なども、違う見方が出来て面白いものですね。
よっしーでした。